生物多様性トライアル市場創設提言
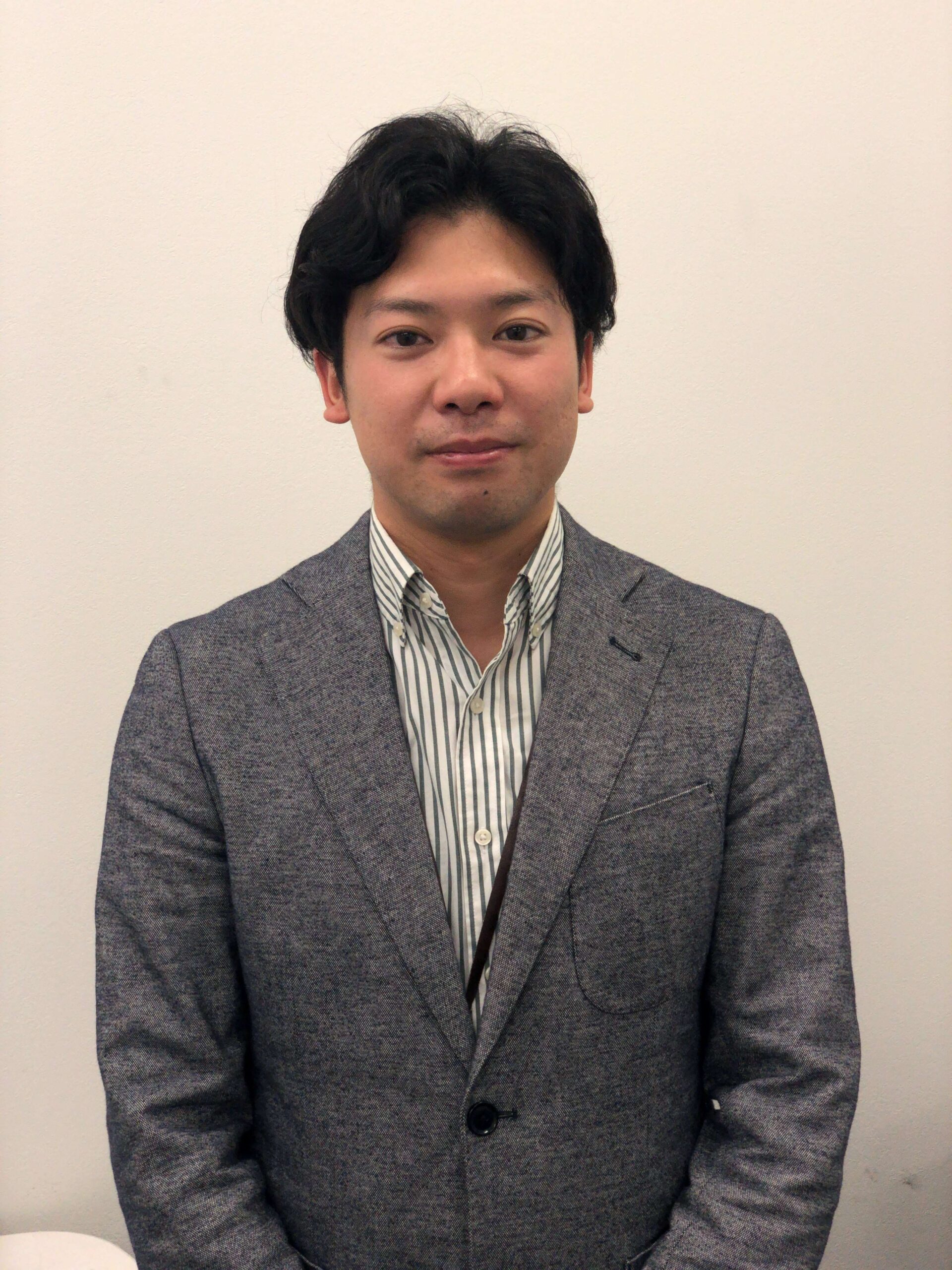 |
田中 雄揮 |
|
PROFILE 佐賀県唐津市生まれ。横浜国立大学経済学部卒。再生可能エネルギー会社にて発電事業開発に従事。同社で実践したバイオガス発電と地域循環型農業の取り組みをきっかけに、持続可能な自然資本の利用に関心を深める。 |
いま起こっていること
気候変動と連動し、自然資本の内部経済化とルールメイキングの流れが世界で進んでいます。特に生物多様性においては、企業の事業活動の影響と評価に関する情報開示のルール策定が欧州を中心に進んでいます。しかしながら日本が古くより育んできた自然観は海外のそれとは異なる部分もあることから、日本企業が世界基準のみに対応すると日本固有の自然観が失われ、日本国内では健全な自然資本保護投資が起きにくいことが懸念されます。国際的な生物多様性の動きに対して、国内では生物多様性国家戦略2023-2030の策定や、生物多様性価値取引市場の創設検討会の動きなどが見られ、また国家戦略の中では生物多様性の取組を、ネイチャーポジティブ(自然再興)のロードマップとして取りまとめ、具体的な目標や行動計画を定めています。
しかしながら今回策定された目標や行動計画は、企業にとって事業利益や機会につながる意義を見出しにくく、事業活動にまで結び付けられていないのが現状です。また世界と比して国内の消費者機運は、積極的に生物多様性の取組を行う商品やサービスへの購買意欲が高いとは言い難く、市場が未成熟な状態です。
上記の状況を好転させ国内の生物多様性の取組を加速するためには、企業の投資意欲を引き出す魅力的な投資・市場創設と消費者意識理解促進による機運醸成が必要だと考えられます。そのため、生物多様性の取組を進める企業や地域の支援や、消費者機運醸成の促進支援などを先駆的に仕掛けたいステークホルダーをトライアル組織・地域として選定し、市場開拓の成功モデルを確立、横展開に繋げることが重要だと考えます。
すでに政府が取り組んでいること
グローバルの生物多様性の議論は生物多様性条約締約国会議(通称COP)にて行われ、直近開催されたCOP15では「昆明・モントリオール生物多様性枠組」が採択されて各国の生物多様性国家戦略及び行動計画と「枠組」との整合性の確認を求めました。これを受けて日本政府は、環境省主導の下、戦略と行動計画を生物多様性国家戦略 2023-2030として策定しています。国家戦略の中では、2050年、2030年を節目に目標が掲げられ、具体的な行動計画では、陸域及び海域の30%を民間管理も含めた保全推進すること(通称30by30)、劣化した生態系の30%以上を再生することなどを掲げています。
めざすべき未来の姿
世界では、生物多様性の取組を内部経済化して指標化したり、評価情報開示に取り込む動きが加速しています。英国など一部地域では、生態系の保全活動を行う企業が生み出した価値を証券化し、市場取引できる制度を確立し市場形成を行っています。一方、日本は古来より生態系豊かな「ホットスポット」を国全体で有する世界でも特殊な地理を持つ国でありながらも、近年の経済成長の皺寄せで破壊された生物多様性の回復における取組が世界から遅れをとっている現状を鑑みると、その対策は急務であると考えられます。
対応の方向性は、2050年に日本が世界を牽引し、地球全体の生態系保全をリードできるように現時点から生物多様性の保全に対する投資を促し、世論の理解度を上げていくことです。現在の人類文明維持をフットプリントに換算すると地球1.8個分の資源及び自然の自浄作用が必要で、これが2050年時点では地球3個分に相当するようになると言われています(2021年:The Economics of Biodiversity: The Dasgupta Review)。そこで2050年にその時点の人口及び文明が必要とするフットプリントを地球1個分に相当させるためには①生物多様性の回復(自浄作用の増加による許容量の増加)と、②自然関連技術社会実装や消費者理解(利用や消費の抑制による消費量の減少)が必要となり、そのための市場創生を現時点から推進する必要があります。
未来のために何をすべきか
| 政策案① | 生物多様性の保全、再生、回復を収益事業として行う先駆的な企業や地域を選定しトライアル支援 |
1)生物多様性トライアル特区の設定
生物多様性を地域単位で取り組む行政区を特区として認定し、規制緩和措置の交渉支援を行います
2)先駆的生物多様性事業のモデル支援
生物多様性を保全しながら収益をあげる次世代のバランス型事業にチャレンジする事業者をモデル事業として認定し、その取組の一部を補助金で支援します
3)生物多様性関連データの公開
生物多様性のデータは多岐にわたり、単体で収集するとコスト高になります。事業者及び地域の取組加速のために必要なデータを必要としているステークホルダーが取り扱えるよう、公的資金でこれまで収集したデータにアクセスできる基盤整備と公開を行います。
4)トップランナー表彰
トライアル特区やモデル事業の中でも優秀な取組をピッチコンテストに招待します。その中で最優秀の取組はトップランナーとして表彰し、賞金や減税措置などを行います。また、この一連のコンテストを企画として公開することで、各企業の啓発にもつなげます
5)オープンイノベーションhubの開設支援補助
生物多様性は地域性があり分散しているため、オープンイノベーションや連携が欠かせません。そこで生物多様性の特性に合ったイノベーションhubを地域ごとに開設し、小規模分散型で地域や企業が連携できる機能を有する取組を補助金にて支援します
| 政策案② | 生物多様性関連技術開発の支援及び、関連商品やサービスの積極購買意欲を醸成する消費者啓発 |
1)研究開発に対する補助金
既存の財やサービスに付帯して生物多様性を保全してフットプリントを減らす技術研究開発を補助します
2)法人税減税及び課税措置
生物多様性関連資材の調達を積極的に推進する企業の法人税を減税します。逆にフットプリントが高い資材を調達する企業には課税措置を行います
3)消費者啓発を目的とするモデル事業支援
生物多様性関連商品やサービスの購買を促す事業を次世代消費モデル事業として採択し、3年の事業補助を行います
4)公教育への連携
次世代の消費者層を担う若年層(小学生〜高校生)に対し、生物多様性国家戦略の内容及び先駆的な取組を一部授業に導入し、公教育と連携しながら意識啓発を行います
5)有志国連携
生物多様性フットプリントの軽減を目指す国と連携し、調達、観光、環境影響評価などのルール整合を図り、国単位で国際世論を形成します
| ①②の政策プロセス |
【短期:~2030年】
現時点では生物多様性は内部経済化されておらず、明確な市場も形成されていません。そこで、2030年までは市場創生が大きな方向性となります。市場創生のため、上記の施策を推進しつつ、その財源は国の予算を念頭にします。具体的な財源は、フットプリントの重い企業への課税、森林譲与税など流動性が低い予算の付け替えを想定します。並行して、市場を刺激するため消費者啓発を公教育に取り入れていくことで、中長期の世論形成に向けた地盤づくりを行います。
【中長期:2030年〜2050年】
2050年のあるべき姿の実現に向けてトライアルで創生した市場を自走化させます。具体的には補助金の撤廃と法整備によって、民主導による市場拡大を支援していきます。
